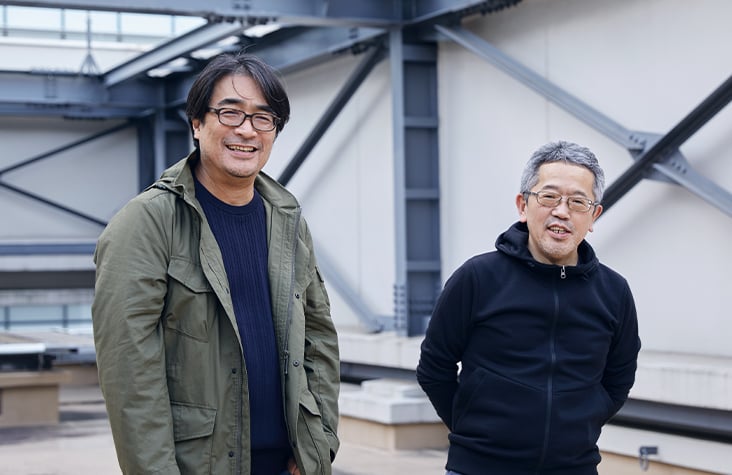紙をめぐる話|紙について話そう。 No.34
|
優れた装丁とインタビューには
そんな共通点があったのかと、
意外な事実に気づかされる対談です。
気取りのない会話の隅々に、
いくつもの印象的な言葉が潜んでいます。
2022年3月30日
初出:PAPER'S No.65 2022 夏号
※内容は初出時のまま掲載しています
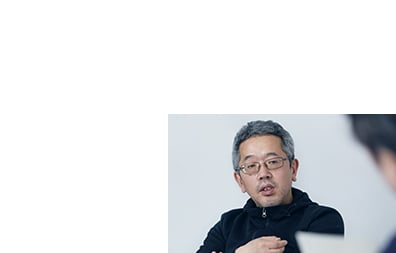
| 鈴木 | 『東京の生活史』(筑摩書房)と並べると、『断片的なものの社会学』(朝日出版社)が文庫本に見えますね(笑)。普通のA5判なのにね。 |
| 岸 | ほんまやなあ。あれ、こんなに小さかったかなあって思いますね(笑)。この『断片的なものの社会学』が、あの、初めて鈴木さんに装丁をお願いしたやつで。2015年。僕ね、デザインがすごく好きで、あがってきたものに納得いかないと、僕やりますわ、言うて自分でやったりもするんですよ。でも鈴木さんには、ほとんど何も言わずにお任せしました。そうしたらもう、素晴らしかった。デザインが中身に合ってるなって、すごいびっくりして。それで、デザインする前に本文は読むのかなっていうのが、今日一番聞きたかったことで。 |
| 鈴木 | 読みますよ。いつも全部ゲラで読みます。『断片的なものの社会学』のときは、50点くらいありましたかね、写真を見せていただいて。そこから原稿の空気感に通じるような何気ない風景の写真をいくつか選んで、偶然性や無名性が紙面から浮かび上がってくるように、最初から最後まであえて同じ大きさで淡々と並べました。普通、本って著者の「俺だ俺だ」って感じが出るじゃないですか。でもこの本にはそれが一切ないわけですよ。たまたま頭に浮かんできたものをぶった切って、断面を覗いてみました、みたいな印象で。 |
| 岸 | テーマなんてなくて、偶然浮かんできて、偶然集まってきたものを本にした感じ。その趣旨を鈴木さんがすごく理解してくれたなっていうか。 |

東京湾の青、半分空気、待つ。
| 岸 | 鈴木さんは最初からそういうやり方だったんですか? |
| 鈴木 | 基本的には頼まれたからやってる。それがずーっと続いてますね。だから、こっちから、こう主体的に表現したいとかいうのがまったくないんですよ。で、デザインそのものに関しては内容が口実になっているというか、まあそこからしか出発しない。だから自己表現ではないんですよね。 |
| 岸 | なるほどなるほど。逆にめちゃめちゃ派手にするときもあるんでしょ? |
| 鈴木 | そうそうそう。要するに本の個性をそこに与えられればいいなと。『東京の生活史』で言うと、この厚さですからねえ。なんもしなくてもいいですよこれ(笑) |
| 岸 | まあそうよな(笑)。ここに来る前に神保町の書店に寄ってきたんですけど、平積みしていただいてて。それだけでかなりの物質感、存在感が……。これだけ3冊くらいなんですよね、他の平積みは20冊くらいあるのに(笑)。補充が大変って言ってました、書店の方が。それからこの、カバーをめくったところの表紙の青は、本文がたくさんの魚が群れでバーっと泳いでるイメージやったんで、夜の東京湾の色にしてってお願いして。 |
| 鈴木 | だから青を二回刷ったんじゃなかったかなあ。深い青がなかなか出なくて。 |
| 岸 | あっ、それはお手数をおかけしました(笑)。これ、紙は作ったんですよね? |
| 鈴木 | ハーフエアっていう紙なんですけれども、かなり昔に、10年くらい前ですかね、僕がアイデアを出して、王子エフテックスさんと一緒に作った紙なんですよね。名前の通り、半分空気が入ってるんですよ。だから軽くてふわっとやわらかくて、ある程度の強度もある。 |
| 岸 | デザインってどこから考えるんですか?紙から?一挙にイメージする感じ? |
| 鈴木 | まず読みますよね。読んで、まあその紙を選んで、絵を選んで、判型を選んで、ぽんぽんぽんぽんっていろんな選択肢があるんですけれども、読んだその感想をその本の個性にしていくためにはどう選択していけばいいか、ということですよね。一挙にイメージするときもありますけれども、まあ探ってるうちに発見したり。例えば、イラストだったらイラストレーターとやりとりしますよね。その中でその本の特徴が掴めてくるとか、実体化するとか……まあ最初はやっぱりぼんやりしてるのが多いかなあ。 |
| 岸 | なんかすごい受け身な感じですよね。向こうから来るのを待つ、みたいな。 |

落差、全力の受け身、反応。
| 岸 | 表現のことでやりあったことあります?著者とか編集者と。 |
| 鈴木 | うーん、ないですね。いや、昔あったかな……まあ理不尽な要求なんかは、若い頃はされやすいんですよ。黒から赤にしろ、とかね。文字赤くしろ、見えづらいから、とか。で、突っ張って喧嘩腰になって、じゃあやめる、みたいなことは昔はありましたけども。まあさすがに最近は「ハイ、スミマセン」ってすぐ変えたりしますけどね(笑)。年相応にこだわりがなくなってる。 |
| 岸 | でもなんかこう、なんやろな……それは単なるパーツみたいになってる人ではないなと思うんですよね。なんか一回ずつ工夫してるし、なんかロジカルやし、スタイルがいつも全然違うのは、むしろ状況に合わせて作れる人なんやなって。 |
| 鈴木 | そうですね、その企画なり内容なりをいかに面白がれるか、ですよね。やっぱり僕自身が発見してるわけですね、その本に対して。専門家じゃないからね。全然知らない世界なので、どんな本でもそこに感動なり関心なりがあるじゃないですか。あらかじめの知識がないまま始めますので、その落差こそがモチベーションというか、デザインのきっかけになるんですよね。 |
| 岸 | なんかね、そういうクリエイターの自意識ってすごい興味あるんですよね。我の作品を作りたいから表現の仕事をしてるんちゃうかなって普通は思うわけですよ。だけど、実際の表現の現場って、むしろ受け身だったりする。鈴木さんと仕事さしてもらってすごいええなと思うのは、こっちの意図を汲んだ上で予想を超えてくるんですよね。これが本当に感動したんですよ。本文に写真を挟む間隔とか、本を開いたときの統一感みたいなのもそうやし、ここまで思ってなかったんで。超えてくるものがあるってことは、やっぱり自意識もあるわけじゃないですか。そういう鈴木成一色を出してくる部分と、現場で発見を待ってるっていう受け身の部分と、両方できる人ってあんまいないと思うんですよね。オープンっていうか、向こうからくるやろ、みたいな。 |
| 鈴木 | 投げ返すからな、みたいなことですよね。 |
| 岸 | なんかインタビューも同じようなところがあって。インタビューのコツってなんにもないんですよ。僕インタビュー下手なんで、すっごい。で、「どんな質問をしたらその人の話が引き出せますか?」とか、よく聞かれるんですよ。でも考えたことないんですよ。だって生活史のインタビューって3時間くらいかかるんで、質問項目を決めずに行かんとしょうがないわけですよ。その場で話してて、次の質問が湧いてくるんです。だからその、ものすごい聞きたいことがあって現場に行ってるんですけど、現場で何してるかっていうとうなずいてるだけ。むちゃくちゃ積極的に聞く気満々で、一生懸命頭下げて菓子折持って、聞かせてくださいって言って現場でうなずいてるだけっていう。すっごい「積極的に受動的」になってるんですよ。全力の力で受け身になってるみたいな感じがあって。クリエイターってそういうとこありますよね。作ってないっていうか、湧いてくるっていうか。職人っちゅうか、なんていうんですかね。 |
| 鈴木 | 職人とまで言うとなあ、なんか守りすぎるところがありすぎるような気がするんですけどね。なかば……反応? |
| 岸 | 反応!反応っていいですね。ああ、反応っていいなあ…… |
| 鈴木 | 反応の仕方がこの職業を選ばせたというか。それは紙であったり文字であったり。その内容に対して反応したものをこう、投げ返すという感じですよね。相手もこちらに反応してるわけで、その中で、なんかなあ、立ち現れるというかね。 |
| 岸 | いつも言うてるんですけど、質問したいことがなかったらインタビューできないけど、インタビューしなかったら質問が出てこないんですよ。だからインタビューの現場、聞き取りっていう実践と、そこで質問したいことっていうのは同時に発生するっていうか。これすっごい変な、不思議なこう、感じなんですよね。聞きながら探ってる、質問しながら質問を考える感じ。で、質問しないと質問できないんで、なんかこう、何してんねやろなといつも思いますけどね。でも反応って言葉は、すごく腑に落ちました。 |

ジャズ、ぬるぬる、逆行。
| 岸 | 僕ジャズやってたんですよ。学生のときにほぼジャズミュージシャンやって、結構飯食ってたんですよ。ジャズって学問じゃないですか。チャーリー・パーカーがいて、マイルス・デイヴィスがいて、っていうのがこう……系統的に続くでしょう。あれがね、僕すごい影響受けてると思うんですよね。アルバムも、アートワークがあって、メンバーが共著者のような関係で、曲が章立てですよね、一曲目が第一章、二曲目が第二章、みたいな感じで。だから昔のインパルスとかブルーノートってすっごいジャケットが綺麗やし。 |
| 鈴木 | かっこよかったですよね。 |
| 岸 | かっこよかったですねえ。自分の本もアルバム単位で作ってる感じなんですよね。前はこうだから、次はこうしよう、次はこうしよう、みたいな。だからゼロから作りたい、トータルで。ほんで、この『マンゴーと手榴弾──生活史の理論』(勁草書房)っていう本は、竹尾の淀屋橋見本帖に行って、紙全部選んだんですよ、自分で。あと、これなんていうんですかね。 |
| 鈴木 | 花布ですかね。 |
| 岸 | そうそうそう。で、見返しをマンゴーの色にして。花布は手榴弾の色にしたんですよ。ものすごい濃いダークグリーン。カバーも白い雲の上に字だけが浮かんでる感じにしたかったんですよ。多分、ジャズのアルバムも、インパルスの妙にぬるぬるした感じとか、紙の処理のつるつるした感じとか、写真の写り具合とか、手に触ったときのものの感じがなんかすごいよかったんだろうと。輸入盤開けたときの匂いとか、ちょっと酸っぱい匂いがするとか。その、物質的なところまですごい興味があって、やりたいなと思ってるんですよね。だから鈴木さんが紙作ったのもなんかわかるっていうか……自分でも紙から作りたいなあって思いましたね。やっぱり紙を作るときは、手触りとか持った感じのことを考えるんですか? |
| 鈴木 | そうだなあ、やっぱりありますね、つるつるしてるだとか、ちょっとこうぬめっとしてるだとか、ぴかぴかだとか、ざらっとしてるとか。紙によって全然違いますから。物ですからね。持ったときの感触というのはやっぱり表面によって全然違ってきますね。あと『東京の生活史』は重さも重要な要素ですよね。製本はどちらでしたっけ? |
| 岸 | これは、えーと、牧製本ですね。 |
| 鈴木 | 牧製本か。よくやりましたねえ、今の電子化の流れに逆行するようなことを……(笑)。 |

残る、郷愁、物質との会話。
| 岸 | 150万字ですからね。『東京の生活史』って普通の本10冊分なんですよ。 |
| 鈴木 | 最初はほんとに「なんだ?」と思いましたね(笑)。やっちゃいましたねえ。 |
| 岸 | やっちゃいましたねえ(笑)。しかもめちゃおもろかったんが、結構ちらほらいるんですけど、Kindleと両方買う人がいて。 |
| 鈴木 | へえ〜。 |
| 岸 | 重すぎて手に持って外で読めないからKindleで読むんだけど、家にも置いときたいから買うって感じの。だからあの、物質ですよね、アナログレコードも結局なくならなかったんで。紙がなくなることはないだろうなって。なんですかね、紙が一番良いんですよね、やっぱり。なんかMacでも、僕オールドMacのコレクターで、めちゃくちゃ昔のクラシック2からバーっとあるんですけど、ああいうのも昔のプラスチックの質感が良くて集めてるんです。でもね、昔のファイルって読めなくなってくるんですよ(笑)。プラスチックの、物質的なガワの部分だけが残って、内部の電子的なデータが読めなくなってる。いまのOSやアプリと互換性がないんです。インターネットでも、もう10年前のものってないんですよ。インターネットって情報が全部永久に保存されるんだって思い込んでたんだけど、データって全部消えちゃうし、昔録った音楽とか聴けなくなってるし。意外に残んないんですよね、電子って。紙が一番残る。汎用性というか、普遍性が一番あるのが実は紙やったんやなって。 |
| 鈴木 | なんかねえ、俺ねえ、郷愁じゃないかと思うんですよ。郷愁って要するに、帰るところですよね。装丁やってて思うんですけどね、最終的に、仏壇とか墓みたいなイメージがあるんですよね。うまくその内容を殺してかたちにできたときは、成功したなと思います。 |
| 岸 | 成仏?(笑) |
| 鈴木 | 仏壇とか墓って死んだ証明じゃないですか。うまく……殺すって言ったら語弊があるかもしれないけどね。それって郷愁なんですよね。いつでも戻れる拠り所みたいな。 |
| 岸 | 子どものときに読んだ本ってビジュアルで覚えてるんですよね、表紙の感じとか。インクの感じとか、字の感じとか。子どものときに文学全集が家にあって、誰も読まなかったんですけど、僕だけ読んでたんですよ。で、『あしながおじさん』がすごい好きやって。今読んだら乙女乙女してて読めないんですけど(笑)、大好きやったんですよ。で、いろんな中のエピソードで今でも好きなものは、ページのどこに書いてたか、まで覚えてるんですよ。紙に書かれた文字っていうのは強力に焼き付いてるんですよね。 |
| 鈴木 | やっぱり物質ですよね。物質と会話してる、みたいな。 |