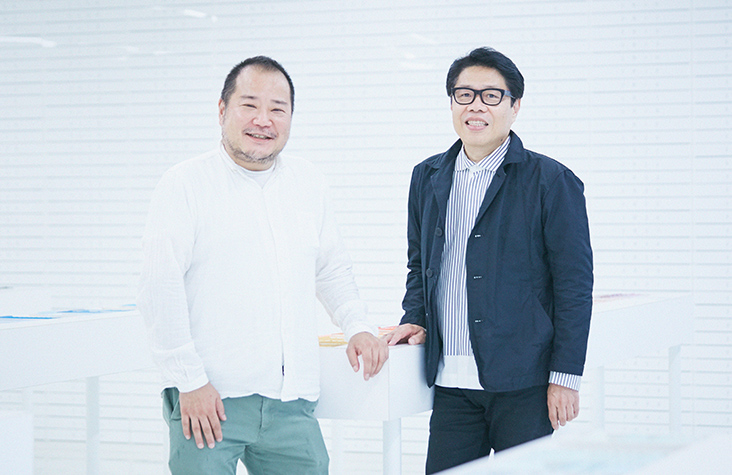紙をめぐる話|紙について話そう。 No.22
|
大阪芸術大学教授の三木健さんと、
東京藝術大学教授の松下計さんの対談です。
教育、デザイン、紙。
話がどこに進んでも、
両教授の目線は常に社会との繋がりを
しっかりと見据えていました。
2016年9月8日
初出:PAPER'S No.53 2016 秋号
※内容は初出時のまま掲載しています

| 松下 | 三木さんはいまの学生たちをどう見ていますか? |
| 三木 | 本気を出すタイミングを待っている印象がありますね。その機会をなかなか見つけられない。でもうまくチャンスを手渡すと、力が伸びるのを感じますね。 |
| 松下 | やる気は満々なんですよね。もうひとつ感じるのが、ボランティアに飛び込む学生が多いこと。ビジネスより先に社会を考えることが自然に備わっているように思いますね。 |
| 三木 | 「みんなと共に」っていう共育ちの感覚が強くなっていますよね。阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本もそうですけど、ソーシャルなものに対しての意識が高くなっている。 |
| 松下 | 僕らの頃は「ここにポスター貼ってください」とか「こういう本をつくれ」というオーダーがまずあって、それを打ち返せばよかった。でも今は最初に何をするかってところから自分でつくっていく。オランダのデザイン教育には「サバイブ(Survive)」というテーマがあって、「あなたの力をどうやって社会に繋げますか?」という問いを常に学生に投げかけるそうです。そんな流れの中にボランティアもあるんですね。 |

気づきに、気づく。
| 三木 | オランダのデザイナーがつくった『PIG 05049』という豚をリサーチしている本が面白い。豚って実は薬やビール、クレヨンの材料にもなっていて、暮らしに深く関係している。これを見ると社会や産業が浮かび上がるんです。 |
| 松下 | 僕がいま学生に一番おすすめの本は三木さんの本ですよ(笑)。『APPLE』はリンゴを色んな角度から眺められるでしょう?まだまだ見方があるよね?ってことを学生は知りたがっていますから。 |
| 三木 | デザインの入口に立っている学生たちに、考え方やつくり方の根源を探ってもらいたくて考えたのが『APPLE』なんです。身体をいかした観察手法や自然界に潜む色の抽出、不自由さの中で見つけ出す物の真意などリンゴについていかに知らないかという「気づきに気づく」ためのプログラムです。ワークショップをするごとに自分を中心としたみんなの活動がファイルに集録されて、最終的に一冊の教科書にまとまる仕組み。こういう授業では、振り返りの作業がものすごく重要なんですよ。 |
| 松下 | 自分を振り返るってことですか? |
| 三木 | はい。理解の巨匠リチャード・ソール・ワーマンが「理解とは、自分が話している内容を第三者が理解したときに初めてできているものだ」と語っているように、自分の言葉で相手に伝えることが重要なんです。 |
| 松下 | そう考えると、振り返りはもはや必修科目ですね。デザイン科ではこれまでは課題の講評でお終いでしたが、いまはさらにもう一回、講評の結果を自分で振り返って説明してもらうようにしています。 |
| 三木 | 学生もそうだし、企業のオーナーたちと話していても、答えはたいてい彼らの中にある。相手からいかに一番いいエキスを引き出すかが大事ですよね。 |
| 松下 | 自分とは違う外の力の中に、うまく自分のスペースを見つけながら走ってゆく。社会に出たらそう生きていかざるをえないし、やらなきゃならない。 |
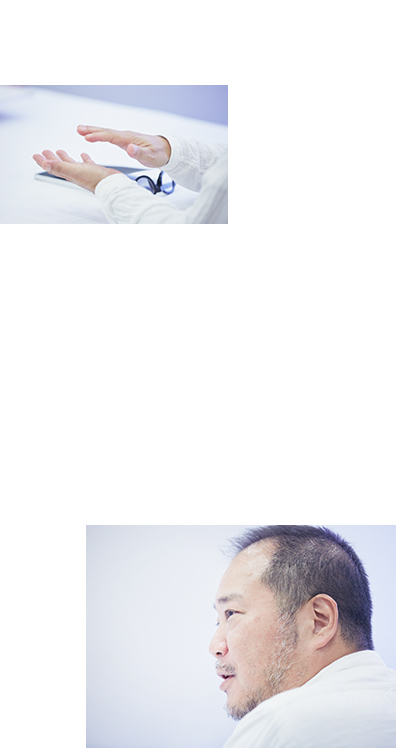
質感の差は、伝わる強さ。
| 三木 | 紙が誰かによってデザインされていることを学生は知らないんですよ。色とか柄とか風合いの差異があることで、印刷した時に表情が変わることも分かっていなかったり。 |
| 松下 | そういう学生もいますね。一方で、いま若い子たちに本が人気なんですよ。手に触れる触感的なもの、書き換えができない不可逆なもの、保存しておくもの、時間軸があるもの……、そういう意味での本に興味がある。デジタルデバイスとの対比で本が浮き彫りになってきたって気がするんですよね。 |
| 三木 | 確かにそうですね。ざらざらとかふわふわとか、指先は脳の延長だから、触れているだけで触発されてくる。 |
| 松下 | 触感と、あと匂いですね。 |
| 三木 | 目に映るものだけがデザインじゃない。例えば都市ガスが嫌な匂いを意図的につけて危険を知らせているのもデザインのひとつ。僕は一年生の最初の授業で、絵を描くことが表現だと思っている学生に見えないものの中にもデザインがあることを話して、価値観を一度逆転させるようにしています。 |
| 松下 | ところで、三木さんの好きな紙はなんですか? |
| 三木 | アラベールですね。自分の封筒も便せんもアラベール。色や風合いのバランスがとてもいいんですよ。以前はステーショナリーペーパーを使っていたんですが、モダンなウォーターマークに変わったのがどうも気に入らなくてアラベールに変えた。ただひとつだけ問題があってね。ペンでサインする時に引っかかってしまう。表情が似ているようでもアラベールは印刷用紙で、ステーショナリーペーパーは書くためのものだから。 |
| 松下 |
僕はヴァンヌーボが好きで、グッドデザイン賞の年鑑向けにヴァンヌーボ スムース-FSをベースにして本文用の紙をつくったんです。産業デザイン振興会(現・日本デザイン振興会)の紙だから「sandesi」って名づけて。それとNTラシャ。一時期、もさっとしていて使いにくいなって思っていたんですが、最近また好きになってきた。 |
| 三木 | 手で触れた時に肌理をすっと感じる、繊細な感じが良いですよね。 |
| 松下 | コミュニケーションって、デジタルのような誰にでも均等に物事を伝えるスーパーフラットなものと、あなただけのために紙もインクも設えましたっていう特別感を伝えるものがありますよね。いま僕は「Earth & Salt」という施設をやっていて、Earthは地球最大単位、Saltは最小単位という意味で、個人の束で社会を捉えようという僕の気持ちを表しているんです。教育も、目の前にいる人の心を動かして、それを束ねることが社会になると考えた方がいいと思うんですね。人を多数でとらえるマーケティングに対して、デザイナーは個人を見る専門家であるべきだと。だからこの微妙なさらさら感、ざらざら感がとっても大事なわけで。 |
| 三木 | 紙って、色・柄・風合いがあってそれぞれ個性が違う。ラブレターを書く時は、品質のある紙を使うよね。 |
| 松下 | 結婚式の招待状はどんな時代になってもEメールでは書かないよ、ってね(笑)。 |
| 三木 | 書かないね(笑)。あ、でも、わかんないな。最近、スーパーフラットな感覚に馴染んで麻痺してる人が多いようにも思う。 |
| 松下 | でもここぞっていうときにはメールじゃ届かない。金箔の封筒でどーんと送ったら読んでくれるでしょう(笑)。大事なときこそ紙がモノを言うんじゃないかな。 |

答えは単純。ワクワクできるか。
| 松下 | 藝大は入学時にはみんな「デザイン科」なんです。将来何がやれるかわからないけど、インテリアもプロダクトの基礎も描画も理論も企画も全部やるんですよ。 |
| 三木 | それは本来の姿だよね。 |
| 松下 | そうなんですよ。デザインの窓口は広いんです。専門に分かれるのは三年生から。だからやっぱり院生が一番手厚くなる、というか時間を割ける。大学院は他校や海外からの学生がたくさんいて、色んな意味で混ざった状態なんですね。で、その混ざるっていうことを最近すごく気に入っていて。まず自分の縦軸=専門性があって、大学院からはそこに横軸を入れる。そういう教育をフィンランドでは「クロスシェイプ」なんていうらしいんですけど、それにまさに近い。藝大は人数も少なく、デザイン科でも芸術家肌が濃い学生が多いんですが、そこに工学系の学生や海外の学生が入ることで、同じ目標のためにスキルを交換し合える。大学ってそれが一番いいのかなって思うんですね。 |
| 三木 | デザイン領域を横断的に捉えることは、当然のこと。芸術と科学の融合と言われて久しいですが、あらゆる分野がクロスするのは特別なことじゃない。暮らしはある意味、クロスの連続ですからね。 |
| 松下 | そう、だからデザインは接着剤的なところがあって、世界や様々な領域をつなぐにはデザインの思想が必要。そういう意味で、教育や研究とすごく相性がいいなって感じます。特にいま、現役バリバリの人が大学で教える時代じゃないですか。 |
| 三木 | 現役バリバリだからいまの社会の動きを敏感に察知できる。いま、ソーシャルやコミュニティやエデュケーションといったデザインを社会が注視しています。そこには、みんなでとかチームでという意識が広がり、社会での存在意義が問われています。よって僕たちがブランディングを組み立てる時でも、理念とその活動を明快にして社会での存在意義をわかりやすく伝えることが求められてきます。そこには、商品やサービスの「品質」と働く人の「誇り」が不可欠になってくる。この「品質と誇り」がやる気やその気や本気といった個人の限界を超えさせるきっかけとなっていく。デザイン教育においても明快な理念に裏打ちされたカリキュラムによって学ぶ人たちの誇りと作品の品質が変わってくる。いかにワクワクする構造を組み立てるか。そこでは、自分ごととみんなとの間を行き来することで何かの気づきに出会えるのです。 |
| 松下 | 藝大では企業や自治体と一緒に行う外部プロジェクトが多いんですが、何か効いていないというか、学生側の効果もあまり上がらない。たぶん、ワクワクしていないんですよ。すごく緻密につくられたプロジェクトでも、肝心の学生が本気で飛び込んでこない。 |
| 三木 | ワクワクするって本当に重要なんです。そこにいけば何かに出会えるかもしれない、自分がひと皮剥けるかもしれないと思えるから努力したくなる。『APPLE』の授業でも、なんとなく赤だと思っていたリンゴの色を徹底して観察してみると自然界にはあまたと色があると気づく。それを知った学生たちに、今度は爪楊枝で点描画のリンゴを描いてもらう。筆で描くのと違ってすごく不自由なんだけど、その不自由さによって全体や部分を見ることを余儀なくされる。すると、なぜか豊かな表情のリンゴに仕上がってくる。人は何かの気づきに出会うとその先の何かを探そうとする。「気づきに気づく」。ここが創造を起動させるスイッチだと思うんです。 |
| 松下 | 普段の仕事もそうなんですよね。答えは単純なところにあって、上手くいったプロジェクトってやっぱり楽しい。学生も議論が白熱するほうが楽しめる。見ればわかるでしょ、みたいなやり方が一番マズいのかな、と思いますね。 |

大局の丘に登って。
| 松下 | ある講演で「専門性に閉じこもらず横と繋がることが大事なんじゃないか」という話をしたんです。ポスターのタイポグラフィの0.1mmを見逃さない世界、これは専門性を深める縦軸として継続しつつ、それをどこにつなげるのかという横軸の両輪が必要になるんですよね。 |
| 三木 |
そうですよね。「着眼大局、着手小局」のように俯瞰する目と細部を徹底して見つめる目。この二つを行き来することがとても大事。「木を見て森を見ず」ではないですが、全体像を把握せずして作業に取り掛かる人が結構います。 僕はいつも学生に「想像の丘に登ろう」と言ってるんです。丘の上から想像すると、向かいたい方向がぼんやりと見えてくる。進みたい方向が決まれば、目標を定めて細部に取り掛かる。何度も想像の丘に登っては、全体の風景を確かめる。それを繰り返すことで打たれ強いコンセプトが生まれるんです。 |
| 松下 | たしかに。全部のコースが混ざっている藝大の一年生時で、すべてに共通しているのはラフスケッチなんですよ。グラフィックやプロダクトなどの専門にいくと、タイポグラフィとかモデリングとか色々と経験するわけですけど、「それって要はこういうことじゃない?」を考えるためのラフはどこでも必要になる。それがデザイン思考の中の「ファーストプロトタイピング」なんですよね。そのビジュアライゼーションはデザインすべてに共通している。 |
| 三木 | エディットする力がすごく重要になっていますよね。優秀なデザイナーは解体して編集する力がものすごくある。 |
| 松下 | いま藝大は東工大と連携しているんですが、藝大生が入るだけでガバッと雰囲気が変わるんですって。書類に絵が入っただけでもすごいイノベーションなんですよ。絵は論文10ページぐらいに相当すると。藝大生も、自分の力がどこで必要なのかがよく分かりましたと言っていて。それがまさに繋がるということで、新しい発見がありますね。 |
| 三木 | 紙でも、ふわふわとかざらざらみたいな、触覚で感じる風合いを図化してみると紙の個性が可視化されてきます。情報を絵にすることで「わかりやすさの設計」になっていきます。 |
| 松下 | デジダルデバイスが発達すればするほど、あらゆるものが基本的に視覚情報でしかないわけで、手触りも匂いもない。視覚以外のものとどうやってコミットしていくかが、これからは重要になりますよね。 |
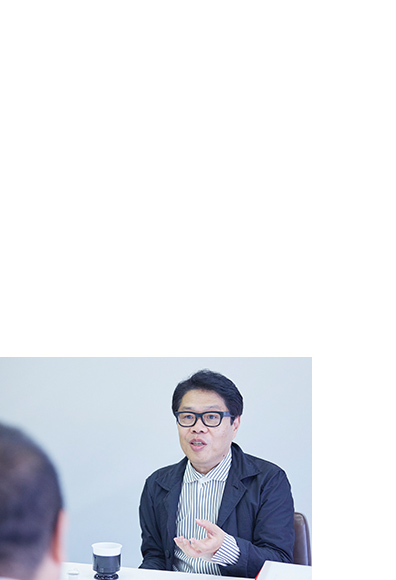
デザインと大学は、これから。
| 松下 | ものすごく高品質な一点物はアーティストがいればできる。大量生産は量産機械なので万単位で物ができていく。1回スイッチを押したらキットカットのようなものは数万個できちゃうんですよ。これからはそんな一点ものと大量生産の中間のところにデザインが入る時代に向かうんじゃないかと思うんです。たぶん、紙も。 |
| 三木 | ある洋菓子のメーカーでは、ショートケーキの味を夏と冬でデリケートに変えているそうです。見た目は変わらないんだけど、人は季節によって求める味が変化するので、見えないところで味覚を調整している。量産品もデジタル技術の進歩と共にきめ細かな表情がつくと思う。その方が、毎日が楽しくなってくる。 |
| 松下 | たとえば台湾では小ロットの印刷物でも面白いもの、いいものであれば受け入れられる市場があります。本当は日本にも同じ素質があるはずですが、大ロットでないと印刷できない事が足かせになっています。小ロットに対応する生産の仕組みがあれば今よりもっと自由に本がつくれるようになるし、自己紹介に自分本を配る、なんてこともできるかもしれない。そういう、いまの現実の生産の現場としてはやりにくいことを、大学であれば企業を巻き込んでやれるかもしれません。報告書を書かなくちゃいけないから面倒くさいんですけど(苦笑)。以前、「すっぴん紙」というのを大学と北越紀州製紙さんと竹尾さんでつくったんですよ。製紙の際に薬品を一切塗らずに紙ができるかっていう実験でした。最初は製紙会社さんも二の足を踏んでいましたけど、やってみたら意外とできた。北越紀州製紙さんの小ロットの紙の機械を使って何ができるのか、っていうのがそもそもの発端で。 |
| 三木 | それは商品化したの? |
| 松下 | 現在ある企業が使っているようです。最初は小さな話でもそれを束ねていくと大きなマーケットになってゆきますのでこういう話は大事にしないといけないと思います。ただ大きなマーケットを相手にするには、提供者の事情で考えるのではなく、その前段階として、元々必要なものって何だったの?この問題の本質ってなんなの?ってことが見える、小中ロットに分けて考えなくてはいけないと思います。そう考えられるようになった時点でデザイナーの知見が十分に使えるはずで、もっとそういう問題解決の現場にデザイナーは関わった方がいいし、教育にも取り込んでゆくべきだと思います。「教育」というのは、ただそれを学生に教えるんじゃなくて、もうそこで企業を相手に実行しちゃうということです。企業に優秀な講師と、彼が引き連れるスタッフを派遣して、そこには学生もいて、利益を出しながらちゃんと年収に見合うくらいのお金を受け取れる仕組みもつくって、大学はそのマージンだけでなんとか生きていく。そんなことをやっていかないと大学ってもう残れないような気がする。 |
| 三木 | たとえば医学や製薬会社と接点をもつようなことをデザインの領域でやっていかないとね。 |
| 松下 | これからはラボみたいに、一緒に何が問題かというところから考えるフレームを大学がつくっていく方向に進むと思いますね。 |
| 三木 | かつての亀倉雄策さんや田中一光さん達は、それぞれの企業としっかりコミュニケーションをとりながら理念とデザインのあり方を経営のレベルにまで持ち上げてきたように思います。デザインにより解決する方法は、企業にとどまらず、政治であろうと街づくりであろうといたるところに必要です。研究機関としての大学が企業とスクラムを組む。学生達も実業を通して学ぶことでリアリティが湧いてくる。 |
| 松下 | 一方で、本質的なことをやるだけでは足りないですよね。新しさがないと人の心は動きませんから。人の心を動かせないとそもそもやる意味がないので、デザインでは新しいもので感動させるってことがマストですよね。役に立つけどまったく感動がなければ、デザインにならない。 |
| 三木 | 新しい価値観、つまり発見を提供することがデザインの役割ですからね。 |
| 松下 | そうですよね。 |