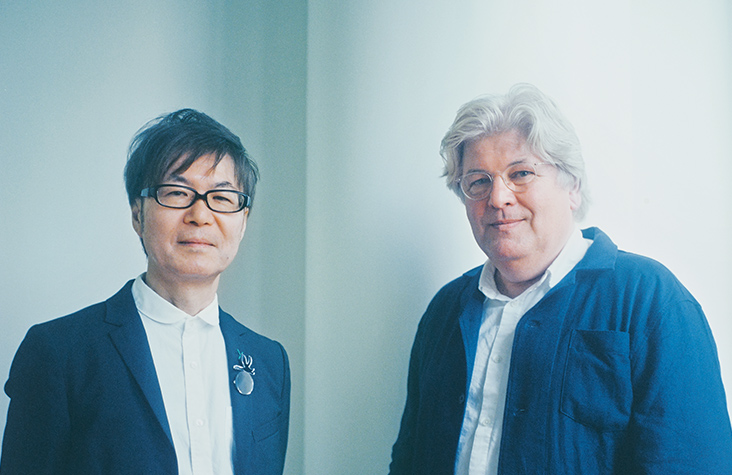紙をめぐる話|紙について話そう。 No.17
|
グラフィックデザイナーとして
活動しながら、自ら出版社を主宰する
松田さんとMüllerさん。
変動する時代の中であくまでも紙の本を
仕事の中心に据えるお二人の話からは、
紙ならではの価値が改めて
浮かび上がってきました。
2014年11月7日
初出:PAPER'S No.48 2014 冬号
※内容は初出時のまま掲載しています
| Müller | 「紙について話そう。」に外国人が登場するのは私が初めてなんですね。でも紙は世界中どこでも紙。まずは二人に共通する本の話から始めましょうか。松田さんはどんな経緯でブックデザインに携わることに? |
| 松田 | 僕は元々グラフィックデザイナーとして仕事をしていました。ある時仕事と並行して活動していたバンドのクリスマスパーティを開くことになったんです。その時にお土産として小さな本をつくったことが出版社としての始まりでした。それから毎年少なくとも1冊は本をつくっています。もっと若い頃にはコンセプチュアルアートをやっていて、その頃にも本をつくっていましたから、それも影響していますね。 |
| Müller | 私も始まりはグラフィックデザイナーでした。当時はまだ25歳くらいの無垢な若者で、スイスとオランダでデザインを学んでいました。ポスター、レコードカバー、本の三つが主な仕事でしたね。スイスで働いていた頃、僧院の図書館に勤めていた友人が、古書が保管されている書庫に内緒で入れてくれたことがありました。そこにはまだ印刷技術がないような数百年前の手書きの本がたくさん保管されていて、それらを夢中になって眺めていたんです。その時「いちばん長く残るものは本だ」と強く感じたことが、ブックデザインの仕事をメインにするようになったきっかけです。83年にはLars Müller Publishersを開設して編集者の仕事も始めました。もちろん本をデザインするのも大好きですから、デザイナーの活動も続けています。 |

五感を触発する本
| 松田 | 薄い紙を束ねて立体にすることでひとつのオブジェになる。僕はそれが本の魅力だと考えていて、ブックデザインをする際の理念でもあります。今後、本の市場が縮小していったとしても紙を素材にした四角形という基本的な形態は変わらないでしょうから、この理念も変えずにいたいと思っています。 |
| Müller | シルキー、フレンドリー、ソフト、スムース……紙の本に触れると様々な質感を感じますよね。これはデジタルタブレットではできない経験です。さきほど僧院の図書館で古い時代の本に触れた話をしましたが、本というのは、当時も今もやはり物質的なリアリティのある存在だと思っています。有機的で、自然や生物と密接に関連している豊かな素材。そのような紙の質感を経験してもらう機会を大切にしていかないと、やがては紙の質の良し悪しが分からなくなる時代がやってくるかもしれません。 |
| 松田 | そこで大事になるのは絵本だと思いますね。子供の頃から紙の本に親しんでいないと、大人になってもその良さが感じられないですから。 |
| Müller | アナログ的な質感の良さが分かるように、紙の本に対するアクセスを増やして、子供たちを根本から育てていく必要がありますね。たとえば手に持ったコップの重さによって中に入っているミルクの量が推測できるように、大きなサイズでありながらとても軽い本を手にすれば、紙に何か工夫がされているということを子供たちは直感的に感じるはずですし、その不思議を楽しんでくれるはずです。コーティングされている紙と、バルキーな紙の触感の違いだって気づいてくれる。大切なのは、そういう刺激を与えるためのチャレンジをデザイナーが続けることではないでしょうか。 |
| 松田 | 五感をフルに駆使する驚きのある本が必要ですね。以前つくった「速度びより」という本では、表紙の芯ボールに穴をあけることで見た目よりもずっと軽くなる工夫をしたんです。 |
| Müller | 本当に飛ぶように軽い。素晴らしいアイデアですね!発見する楽しさがあって、感覚的な喜びを感じられますね。私も真似してみようかな(笑)。 |

Instrument to Document
| Müller | これからのデザイナーは、紙の会社と手を組んでデジタルにはないリアリティのあるものを残していく必要があります。物質的なつながりは感覚的なつながりにもなる。誕生日に祝いの気持ちを伝える時もメールより手紙の方が感謝されますし、長くも残りますよね。 |
| 松田 | 断捨離という言葉がありますが、捨てるもの、残さないものとしてデジタルは有用だと思います。でも確かに大切なものを記憶や感覚に残すためには、紙のような質感のある素材でないと難しいですよね。 |
| Müller | ヨーロッパの図書館では、塩素などの化学的な原料を使った本を所蔵しません。数百年後まで本を残すためにするべきことを、きちんと考えているんですね。ただ一方で、私自身がつくってきた本を振り返ると、本当に後年まで残すべき価値があるのかどうか疑わしくなる時もあります。高級な紙で立派な本を印刷しても、高級紙に見合うほどの内容だったのかどうかと。 |
| 松田 | 確かにその時は有用な本でも、後々に無用になることはありますね。 |
| Müller | そうなんです。たとえばコンテンポラリーアートの本は、どうしてもその時代に流行している内容を掲載しますよね。だからつくった瞬間は新しくても、数年後には魅力が色褪せてしまっていたりする。そんな時は「雑誌に任せればよかった」なんて後悔します。 |
| 松田 | 僕も執筆した本を読み返した時、当時の自分の知識不足を感じることがあります。デザイン以上に情報は移り変わりが激しいですからね。 |
| Müller | 一方で、古い時代の情報が後世になって再び必要とされる場合もありますね。つまり本はまず読者を触発するためのInstrument(道具)としてその時代で力を発揮し、時代が移った後はDocument(記録、文献)としての役割を担うようになる。2004年に人権に関する本をつくったことがあるのですが、それは当時の政治家を内容的にも物理的にもノックダウンできるくらいに重みのある、武器のような本でした。今では武器としての役目は無効となりましたが、その当時の世界における人権の様相を伝える貴重なドキュメントになっています。これは紙の本だからできることです。デジタルにも変革を起こす力はありますが、すぐに上書きされ埋もれてしまいますから、ドキュメントとしては残らないんですね。 |
| 松田 | ドキュメントにはなり得ないかもしれませんが、デジタルは紙の本のようなアナログ的なものを長く残していくためのプロセスとして役立つ存在だと思います。たとえば僕は牛若丸出版を起ち上げて間もなく、まだ世の中に出回り始めたばかりのDTPを導入したのですが、それは写植にかかるコストを減らすことで、紙の本がより出版しやすくなると考えてのことでした。 |
| Müller | デジタルプロセスによって逆にアナログが活きるといえば、書体も似たような状況にありますね。デジタルの時代になるとデジタルらしいまったく新しい書体が登場するかと思ったら、それ程でもなかった。実際には古いものが良しとされ、デジタル上でも使い回されているケースが多い。 |
| 松田 | 日本でもほとんどが活字をベースにしたデジタル書体が使われていますね。結局、デジタルとアナログは対立するものではないのかもしれません。紙の本にしても、デジタルの台頭をマイナスに考えるのではなく、むしろそれを上手く活用することが長く残していくために本当に必要なことでしょうから。 |

デザイナーが試されている。
|
Müller |
松田さんのデザインは私よりも実験的ですね。私の場合はまず経済性とのバランスを考えます。中央ヨーロッパでは、本は工業製品のひとつとして位置づけられていますから、コストに対する制約がより強いんです。一方でアジア、たとえば日本の伝統的な本のつくり方は素晴らしいと思います。質が高く、オリジナリティがある。大量生産される本でもそれが変わらないのは驚きです。竹尾の紙見本を眺めて「この紙を使いたい」と考えても、ヨーロッパではなかなか経済的に見合わないことが多いんです。 |
| 松田 | 最近は日本でもコストダウンが叫ばれていますから、特に本文用紙は価格の低い紙を使うように言われます。でもそれは逆にいうと、デザイナーの力量が試される時代になったということでもあるはず。高価でない紙でどこまでできるのかと。 |
| Müller | 本文でコストに配慮した紙を使用すると、印刷面で問題が出てくることがありますよね。そんな時はどうしていますか。 |
| 松田 | インキで工夫する方法もありますよね。たとえばカレイドインキは、コーティングしていない紙に載せてもそうとは思えないほど発色がいい。インキの進化はこれからもっと加速していくような気がしています。 |
| Müller | 確かに印刷業界も進化していますね。でもさらなるイノベーションを追求してほしいし、それを私たち自身が促さなくてはいけない。自動化や最適化ではない根本からの革新が必要です。オフセット印刷にしても、デジタル印刷に対抗できるくらいの進化がほしい。コンビニの食事よりもおいしいものが食べたいと誰もが思うのと同じように、印刷についても当たり前のように質を追求する時代にしていきたいですね。 |
| 松田 | 本に印刷の質を求める読者は確実に増えていると思います。出版側からは無理でも、読者側からの促しによって印刷は自然と発展していくはずです |

日本の紙は、日本そのもの。
|
Müller |
日本やイギリスのような島国は本文用紙にもバラエティがありますね。中央ヨーロッパでは印刷代が節約できないので、どうしてもそのしわ寄せが紙にきます。だから紙の種類を維持するのはとても難しい。たとえばスイスでは以前の半分くらいになってしまっている。製紙メーカーも三社ほどしか残っていませんし、どこも似た紙をつくっているので選択肢も少ない。一方で竹尾は「紙の出版社」という感じがしますね。「ペーパープロダクター」と呼んでもいいかもしれない。 |
| 松田 | 本当に種類が豊富ですよね。竹尾の紙の中では、僕は特に「ヴァンヌーボ」が好きですね。紙の風合いと印刷適正という相反する性質を両立させていて、大発明だと思います。クラフト紙も好きですね。 |
| Müller | 私はコーティングのないバルキーでスムースな紙が好きなのですが、それはヨーロッパにあまりない、非常に日本的な感じのする紙なんです。ですから竹尾には、ぜひとも今の姿勢で続けていってほしいと思いますし、もっと紙をヨーロッパに輸出することも考えてみてはどうでしょうか。ところで松田さんは、牛若丸出版を海外進出させたいとは思いませんか? |
| 松田 | 個人的な趣向になりますが、本は日本語で読みたいという気持ちが自分の中一番にあるんです。英語の本をつくりたいと思うこともありまが、どうしても日本語を入れたくなってしまって。 |
| Müller | それもわかります。でもチャレンジしてみはいかがでしょうか。ヨーロッパやアメリカの書店では既に日本の本がたくさん並んでいます。主には建築やデザインの本ですが、現地のデザイナーは日本の本を見て「この紙いいな」と感心することが多いんです。その繊細さと洗練は、日本自身を体現しているようにも私は感じています。こうした本を通じた文化交流がもっと増えていけば素晴らしいことだと思うんです。 |